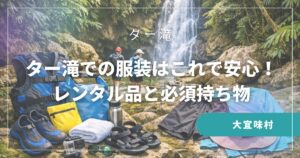沖縄の青い海を見下ろす残波岬の銅像を前に立つと、ただの観光スポット以上の意味を感じました。
残波岬の銅像は誰が建てられ、どんな歴史を持つのか…。この記事ではその背景や文化をやさしくまとめています。知ってから訪れると景色がもっと特別に見えるはずです。
- 残波岬の銅像とは?その由来や象徴する意味が理解できる
- 何をした人?銅像の人物・泰期の功績がわかる
- 残波岬の歴史とは?沖縄戦や灯台の成り立ちに触れられる
- 石積みやシーサーなど文化と観光の魅力を知ることができる
- 残波岬 銅像の歴史と由来を徹底解説
残波岬の銅像の歴史と由来を徹底解説

沖縄本島の西海岸に立つ残波岬の銅像は、歴史的背景と文化的意味を持つ象徴的な存在です。観光だけでなく学びの場としても注目されています。
- 残波岬の銅像とは?
- 何をした人?銅像が建てられた人物と功績
- 残波岬の歴史とは?
残波岬の銅像とは?

残波岬の銅像は、読谷村(ゆんたんそん)出身の英雄・泰期(たいき)を称えて建立された像です。
像は高さ約180cmで、右手を伸ばして中国福建省の方向を指しており、これは泰期が中国との交易に尽力したことを象徴しています。
この像は、読谷村の村制100周年・商工会35周年を記念して2008年に完成したもので、残波岬公園の敷地内にあります。
何をした人?銅像が建てられた人物と功績
この銅像は、読谷村(よみたんそん)出身の 泰期(たいき) を称えて建てられたものです。
泰期は14世紀後半、当時の中山王(ちゅうざんおう)・察度(さっと)の命を受けて、初めて中国(明)への進貢(朝貢使)として派遣された人物です。
危険を伴う航海を繰り返し、少なくとも5回は中国と行き来したと伝えられ、その交易によって琉球(沖縄)の発展にも寄与したとされています。
また、泰期は「商売の神様」として地域で尊ばれ、読谷村の産業振興・文化の象徴としても位置づけられています。
残波岬の歴史とは?
残波岬(ざんぱみさき)は、沖縄県読谷村(よみたんそん)にある岬で、東シナ海に向かって突き出した地形が特徴です。
岬の断崖(だんがい)は高さ約30メートル前後、長さおよそ2キロメートルにわたり連なっており、荒波が岩にぶつかって飛沫(しぶき)をあげる光景が見られます。
さらに、残波岬は沖縄戦の時代にも歴史的な役割を果たしました。1945年に米軍が読谷海岸に上陸する際、この岬が目印になったと伝えられています。
戦後、岬の突端には灯台が設けられ、1974年(昭和49年)3月30日に初点灯しました。
また、岬周辺は沖縄海岸国定公園の一部となっており、自然景観の保存と観光利用が両立されてきました。
▼関連記事
「残波岬 怖い」と検索されるワケ|過去の事件と心霊現象追う
残波岬の銅像から学ぶ沖縄文化と観光の魅力
銅像は単なる記念碑ではなく、地域の文化や信仰を映し出す存在です。残波岬を訪れることで歴史と観光を同時に楽しめます。
- 石積みとは?なぜ残波岬に築かれたのか
- 残波岬のシーサーとは?
- よくある質問(アクセス・所要時間・駐車場など)
石積みとは?なぜ残波岬に築かれたのか
「石積み」とは、小さな石や岩を重ねて積み上げる構造や造作のことを言います。沖縄各地では祈りや信仰、死者供養、魔除けなどの目的で、「積石(せきせき)」と呼ばれる形で自然発生的に石を積む風習があります。
残波岬では、断崖付近や灯台周辺の広場近くで、小さな石積みを見かけることがあります。地元や訪問者の間では、これらが「神を祀る」「死者を追悼する」意図をもって置かれたものではないか、という解釈が語られています。
残波岬のシーサーとは?

残波岬公園の入口近くには、「残波大獅子(ざんぱおおじし)」と呼ばれる巨大なシーサー像があります。
このシーサーは高さ約8.75メートル、長さ約7.8メートルと、沖縄県内でも最大級のサイズを誇ります。
通常、シーサーは魔除け・守り神として家の屋根や門に置かれ、邪気を防ぐ役割を担います。
ですが、残波大獅子はそれに加えて、読谷村がかつて中国との貿易によって栄えた歴史を後世に伝える象徴として、1985年(昭和60年)頃に建立されたと言われています。
さらにこの像は、一般的なシーサー像とは異なり、中国大陸の方向を向いて設置されている点も特徴です。これは、貿易や文化交流を重視した意図を込めた配置とみられています。
また、大獅子の構造は鉄骨の骨組みにコンクリートを盛るような方法が採られており、非常に頑丈に造られていることが、近くで見ると分かるとの記述があります。
よくある質問(アクセス・所要時間・駐車場など)
- 残波岬へのアクセス方法は?
-
那覇空港から車で約1時間(一般道・高速道路利用)です。
バスを使う場合、空港リムジンバスで「沖縄残波岬ロイヤルホテル」まで約90分程度、その後徒歩で残波岬へ向かう方法もあります。 - 残波岬を観光するのに必要な所要時間はどれくらい?
-
岬の遊歩道を歩き、景色を眺めながら散策するだけなら 30分~1時間 程度が目安です。
灯台に登る場合は、登り降りや風景を楽しむ時間を加えて さらに30分前後 を見ておくと余裕があります。 - 駐車場はありますか?無料ですか?
-
はい、残波岬には 無料駐車場 が複数設けられており、約100台ほど駐車できる規模との情報もあります。
ただし観光シーズンや夕暮れ時などは混み合うため、早めに到着することをおすすめします。
まとめ 残波岬の銅像
ここまでの内容を簡単にまとめると、残波岬の銅像は観光の目印である以上に、沖縄の歴史や文化を映し出す象徴的な存在でした。実際に訪れてみると、ただの石像というより、土地の記憶や人々の思いが重なっているのを感じます。
泰期という人物の功績や、中国との交流に果たした役割を知ると、銅像の立ち姿が急に生き生きと見えてきます。また、岬の断崖と荒波の風景に歴史を重ねると、観光で歩いているだけでは気づけない深さがあるんですよね。だからこそ、この地を訪れるときは背景を知っておくことが本当に大切だと思います。
では、とくに重要なポイントを絞ると以下の通りです。
- 残波岬 銅像は読谷村の英雄・泰期をたたえるために建てられた
- 泰期は14世紀に中国との交易を開き、琉球発展に大きく貢献した
- 残波岬は沖縄戦の上陸地としての歴史も持ち、戦後は平和祈念の地となった
- 公園内には巨大なシーサーや石積みもあり、文化や信仰が息づいている
- アクセスや滞在時間、駐車場など観光に役立つ実用情報も整っている
こうして振り返ると、残波岬はただの絶景スポットではなく、歴史を学び、文化を体感できる場所でした。私自身も次に訪れるときは、もう一度銅像の前に立ち、泰期の視線の先にある海をしっかり眺めてみたいと思います。背景を知ったうえで見る景色は、きっと前よりもずっと特別に映るはずです。
参照元